小学生のお子さんが宿題をやらず、毎日の声かけに疲れを感じていませんか?
「何度言ってもやらない」「また今日も怒ってしまった」そんな日々から抜け出したいと思っている親御さんは多いはず。
この記事では、二人の子どもを育てる中で試行錯誤してきた実体験をもとに、小学生が宿題をやらない理由や対処法、家庭でできる工夫を解説します。
叱らずに、子どもが自分から宿題に取り組むきっかけが見つかるはずです。日々のヒントとして参考にしてみてくださいね。
宿題をやらない原因とは?
小学生が宿題をやらない理由
小学生の子どもが宿題をやらないのは、「面倒だから」「やりたくないから」だけではありません。授業でわからなかった内容がある、疲れて集中できない、ゲームやYouTubeの誘惑が多いなど、いろいろな理由がかくれています。
宿題はやらされるものと感じてしまうと、やる前から気持ちが沈みがちに。親が何度も「早くやりなさい」というほど、逆に反発したくなってしまうのです。
学年別によくある傾向の違い
低学年のうちは遊びたい気持ちが強く、宿題をあと回しにしがちです。
中学年になるとYouTubeやゲームに夢中になり、「あとでやる」と言いながらそのまま忘れてしまう場合も。
高学年になると反抗期がはじまり、「自分のことに口出ししないで」と反発する姿が見られるようになります。
このように、子どもが宿題に向き合わない理由は年齢によっても変わってきます。子どもの性格や成長段階に合わせて、声のかけ方や接し方の工夫が大切ですね。
やる気が出る環境づくり
「宿題やった?」を言わないよう意識する
子どもの宿題には、声かけより見守る姿勢が大切です。
「早くやりなさい」と言いたくなりますが、子どもは親の言葉にとても敏感。口を出されるとやる気をなくしてしまうときもあります。
わたしも子どもに、「宿題やった?」「早くやりなさい」と言われるのが一番イヤだとはっきり言われたことがあります。自分でやる時間を決めていたのに、親が知らずに口を出すと、やる気がしぼんでしまうそうです。
大人でも、仕事から疲れて帰ってきたときに「ご飯まだ?」と聞かれると、なんとなく嫌な気持ちになりますよね。30分だけ休んだら作ろうと思っていたのに、ペースを乱されるとやる気がなくなってしまうのと同じです。
自分でスケジュール通りにできるタイプの子には、なるべく口出しせずに、信じて見守ると良いでしょう。
一方で、宿題をあと回しにしてゲームに夢中になってしまうタイプの子には、「宿題をやるタイミングはまかせるけど、終わるまではゲーム禁止」というルールを徹底しました。
「今日はお友達が遊びにくるから特別に」などの例外は一切つくらず、親のブレない姿勢を大切にしています。この積み重ねで、少しずつ習慣として定着してきました。
タイプに合わせた関わり方と、親の一貫した姿勢が、宿題習慣を育てるカギになります。
集中できる場所を用意する
宿題に集中させたいなら、まずは「環境づくり」からはじめましょう。
子どもはちょっとした音や視界の変化にも敏感で、テレビの音やおもちゃが目に入ると、集中力が続かなくなってしまいます。
どんなにやる気があっても、気が散る環境では勉強に身が入りにくいものです。
我が家では、リビングの一角に折りたたみ机と椅子を置いて、文房具だけをそろえた「宿題コーナー」を作りました。とてもシンプルなスペースですが、自然と気持ちの切り替えがしやすくなったようです。
兄弟がいるご家庭なら、ひとりになれる静かな時間帯を作る工夫もおすすめです。子どもにとって集中しやすい環境作りが、宿題をスムーズに進める第一歩になります。
怒る前に知っておきたい注意点
「叱る」より先に「褒める」
宿題を習慣化するには、とにかく褒めることが効果的です。
子どもは、できたことを認めてもらえると「もっとやってみよう」と前向きになれます。
逆に、注意や指摘ばかりが続くと、やる気はどんどん下がってしまいます。
わたし自身、日頃から「えらいね」「すごいね」といった声かけを意識しています。自分から宿題に取りかかったときはチャンスです!
「えらいね!先にやったから、あとはのんびりできるね」と声をかけたり、「宿題早く終わったから、おやつタイムにしようか」と誘ったりすると、子どもも嬉しそうにしています。
この積み重ねが、「宿題を先にやると良いことがある」と自然に感じられるきっかけになります。叱るよりも、褒める声かけが、子どものやる気を育てる近道です。
信頼関係を壊さない対応とは
宿題の声かけでもっとも大切なのは、信頼関係を壊さないことです。
親がいつもピリピリしていると、子どもは「また怒られるかも」と感じて本音を話さなくなってしまいます。一度信頼が崩れてしまうと、宿題だけでなく、学校での困りごとや友達との悩みも話さなくなる可能性もあります。
わたしは日頃から、どんな話も否定せずに、子どもと同じ目線で受けとめるよう意識しています。「今日は疲れたからやりたくない」と言われたら、「そっか、今日は疲れたよね。ゆっくり休憩してね」とまずは寄り添う。子ども自身も、心のどこかで「宿題をやらなきゃ」と思っています。自分のタイミングでやる気が出るまで休ませてあげる時間も大切だと思うのです。
本音を話しやすい雰囲気と、受けとめてくれる安心感があれば、子どもは自分から動き出す力を育てていきます。信頼関係は、日々のささいなやりとりの中で少しずつ育まれていくものです。宿題の時間も、信頼を築いていく大切なきっかけになるはずです。
生活リズムから見直す方法
時間管理力を育てるコツ
子どもの時間管理力は、親と一緒に育てていくものです。
時間を守る、計画的に動くといった力は、自然に身につくものではなく、日々の関わりの中で少しずつ育っていきます。
「◯時からは宿題の時間ね」と毎日決まったスケジュールを親子で決め、タイマーを使って「この時間だけ集中しよう」と声をかけると、時間を意識する習慣がついてきます。
我が家では、夕飯までに宿題を終わらせる流れを整えた結果、生活リズムが安定し、子どもも自然と机に向かうようになりました。
毎日少しずつ積み重ねる習慣によって、時間の使い方も徐々に身についていきます。
親子で作る平日ルーティン
宿題を習慣にするには、親子で平日のルーティンを作ると効果的です。
毎日その場の流れで動くより、いつも通りのパターンがあることで、子どもは安心して行動できるようになります。ルーティンが決まっていれば、今は何をする時間なのかがわかりやすく、自然と切り替えができるようになります。
たとえば、「宿題→遊び→夕食→自由時間」や、「帰宅→おやつ→宿題→夕飯」といったように、平日の流れをあらかじめ親子で話し合って決めておくとスムーズです。
我が家では、放課後の流れを紙に書いてリビングに貼っています。見える化したことで声かけが減り、子ども自身が時間を意識して動くようになりました。
親子でルーティンを作ることで、生活にリズムが生まれ、宿題も無理なく習慣になっていきます。
【まとめ】宿題をやらない悩みは、親の関わり方で変わる
どんな子でも、親の接し方や声のかけ方ひとつで少しずつ行動は変わっていきます。
まずは今日から、「宿題やった?」の代わりに「今日はどんな1日だった?」と声をかけてみませんか?子どもの受け止め方が変わり、自分から話したくなるきっかけにつながります。
親子の信頼関係を少しずつ育てながら、やる気につながる声かけや関わり方を積み重ねていくと、子どもはやがて自分で考えて動けるようになります。子どものペースを大切にしながら、必要なときにはルールをしっかり決めて、例外を作らず守ることも大切です。
焦らず、できることから一歩ずつはじめていきましょう。あなたとお子さんの毎日が、少しでも楽になることを願っています。
親が無理にやらせるより、「子どもが自分からやりたくなる」仕組みが鍵。
そんな視点で選ぶ習いごとのひとつが、思考力や創造力を育てるプログラミングです。
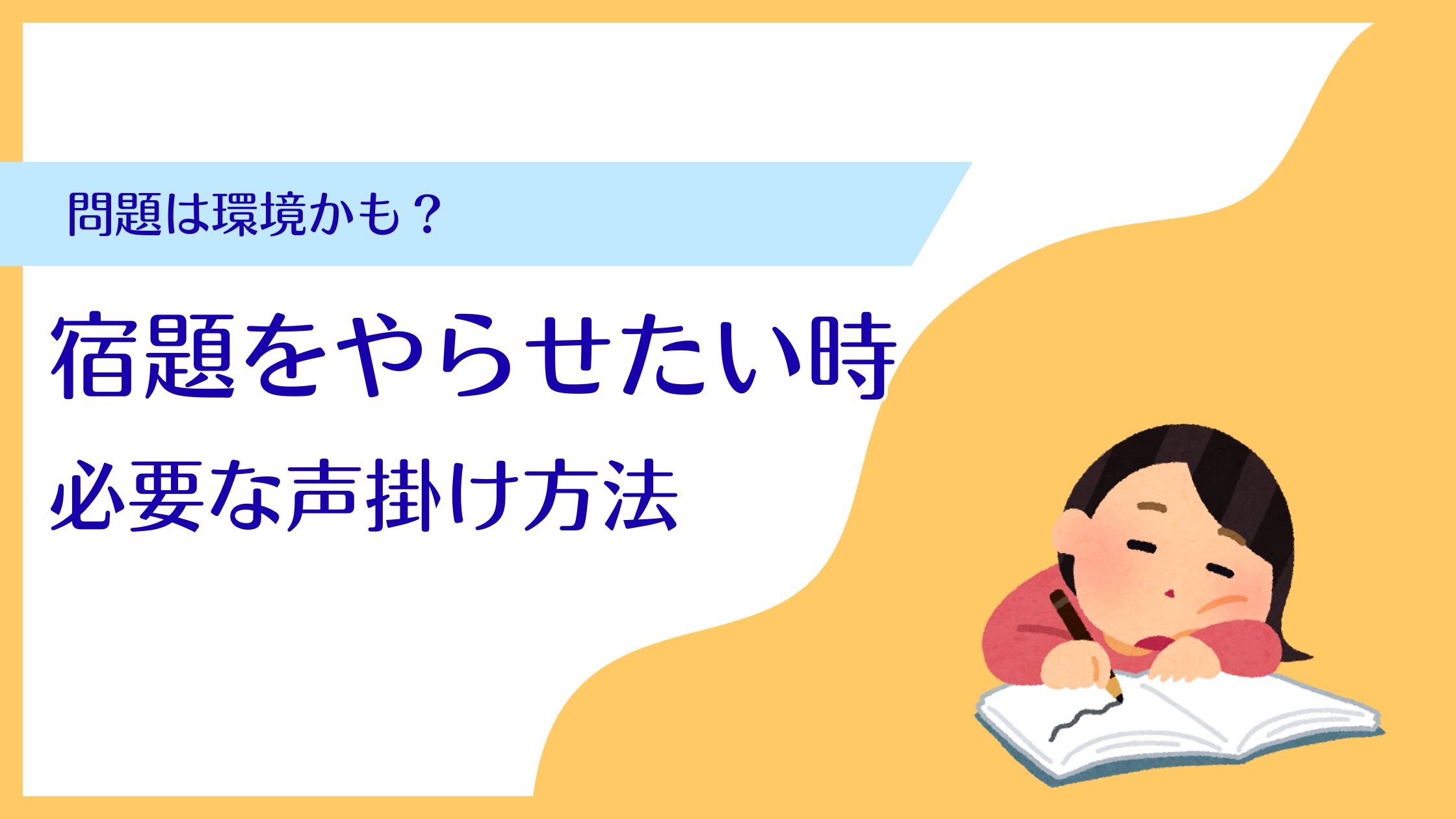


コメント