小学生の子どもにお手伝いをしてほしいけれど、声をかけてもなかなか動いてくれない……そんなモヤモヤを感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、子どもと一緒にルールを決めながら取り組める「ポイント制度」を活用した、わが家のお手伝いの工夫をご紹介します。
低学年の頃からこの方法を続けてきたわが子は、現在6年生。お手伝いはすっかり日常の一部になり、自分の仕事として責任を持って取り組んでくれています。
子どもが自分からお手伝いをしたくなる仕組みがわかり、親子で楽しくお手伝いが続くヒントが見つかるはずです。ぜひ参考にしてみてください。
小学生のお手伝い、どうしてる?
親の「やってほしい」と子どもの本音
忙しい毎日の中で、少しでいいから手伝ってほしいと思うことはありますよね。
でも現実は、「え〜なんで?」「あとでやる〜」と逃げ腰になる子どもたち。
ある日、「どうしてやりたくないの?」と聞いてみたところ、「面倒くさいし、失敗したら怒られるだけだもん」と。
たしかに、できて当たり前のような空気になっていたかもしれません。
頼んでもやってくれない。やっても雑に済ませて余計に手間がかかる。口うるさく言ってケンカになる……。 そんな経験をしたことがある親御さんはきっと多いはずです。
我が家の解決策は「ポイント制度」
お手伝いをさせたいのに、やらせたことで親子関係がぎくしゃくするのは本末転倒ですよね。もっと前向きに、楽しく取り組める方法がないかと考えた末にはじめたのが「ポイント制度」です。
ポイント制度とは?
ポイント制度とは、子どもがお手伝いをするたびにポイントをためられる仕組みです。
ただやるだけで終わらせず、がんばりを見える化することで、子ども自身のモチベーションにつながります。我が家では、毎月のポイント合計を1ポイント=1円としてお小遣いに換算する仕組みにしました。
お手伝い内容とポイント数は子どもと一緒に決める
制度をはじめるときに大切にしたのは「親が一方的に決めない」こと。
・どんなお手伝いができそうか?
・難しさや時間に応じて、何ポイントが妥当か?
これらをすべて子どもと一緒に話し合って決めました。
こちらは我が家の一例です。
| 10ポイント | 20ポイント | 30ポイント | 50ポイント | 100ポイント |
| 食器はこび | ゴミ出し | お皿洗い | ご飯作り | テスト100点 |
| 花の水やり | 布団セット | 洗濯たたみ | 洗濯干し | 犬の散歩 |
| 玄関掃き | 階段水ふき | お風呂掃除 | 乾燥機片付け | |
| テーブル拭き | 靴あらい | マッサージ | 床の水ふき |
難しさや手間に合わせて、ポイントにも差をつけています。我が家では、「テストが表裏どちらも満点で、ボーナス100ポイント!」という、勉強の意欲へつながる仕組みも取り入れました。自分で内容やルールを決めたぶん、自然と責任感を持って取り組んでいます。
お手伝いの内容とポイント数は見えるところに貼っておく
お手伝いの内容とポイント数は、紙に書いてリビングの壁にペタッと貼っています。いつでも見られる場所にあると、「今日は何をしようかな?」と自分からチェックし、お手伝いを探してくれるように。親も一緒に確認しやすく、お手伝いが終わると「ありがとう!」と声をかける流れが自然にできました。
1ポイント=1円でお小遣いに反映
ポイントは月末に集計し、1ポイント=1円で現金に換算して渡します。
我が家では、子どもの年齢に合わせて「上限」を設けました。
- 低学年:最大1000円まで
- 中学年:最大2000円まで
- 高学年:最大3000円まで
このルールがあることで、やりすぎを防ぎながら、達成感やお金の価値についても自然と学べるようになりました。金額の設定は家庭によって考え方が異なるので、無理のない範囲で家族みんなで話し合って決めるのがおすすめです。
貯めたポイントを欲しいゲームやおもちゃと交換するなど、お金以外のごほうびにする方法も、取り入れやすくて楽しいですよね。
ご褒美にもしつつ、防犯機能としても使える一石二鳥のこんなものもあります👇![]()
家庭によって楽しめるルールの工夫を取り入れるのもおすすめです。夏休みや冬休みなどの長期休暇には上限金額を引き上げたり、特別なお手伝いにはボーナスポイントをつけたりすると、子どものやる気アップにもつながります。
ポイント制度を導入してよかったこと
子どもに責任感が生まれた
最初は軽い気持ちではじめたお手伝いでも、自分がやる仕事という意識が芽生えてきました。「洗濯物あとでたたむから、やらないでね!」と自分から言ってくれるように。小さなことでも任せてもらえる経験が、責任感を育てているように感じます。
自分からお手伝いするようになった
ポイントがたまっていくのがうれしいのか、「何かやることある?」と自分から声をかけてくれるようになりました。「これやったら何ポイント?」と聞いてくる姿も微笑ましいです。子ども自身がやることを選べるため、お手伝いが自然な習慣になっています。
親子のコミュニケーションも増えた
「今日は◯ポイント分がんばったね!」という会話や、「いつも助かってるよ」という感謝の気持ちを言葉で伝える習慣も生まれました。
お手伝いがきっかけで、親子の絆が強くなったように感じています。
なぜポイント制は子どもにも続けやすいの?
がんばりが見える化されるから
子どもは成果が目に見えると、やる気が続きやすいもの。ポイントという数値でがんばりが記録されると、ちゃんとできてる!と実感できます。達成感や自己肯定感につながり、自然とまたやろうと思えるのです。
自分で選べるから
あらかじめお手伝い内容を決めておく中で、その日の気分や予定に合わせて「今日はこれにしよう」と選べる自由があると、”やらされている感”が減ります。やらされるのではなく、自分で選んだという感覚があることで、主体的に取り組めるようになります。
小さなごほうびが楽しみになるから
報酬という形で努力が認められるのは、子どもにとってとても嬉しい経験です。自分のがんばりに価値があると実感でき、もっとポイントをためたいという気持ちが芽生え自然とお手伝いが続いていきます。
親からの「ありがとう」が増えるから
「今日も手伝ってくれて助かったよ」と声をかけられることで、子どもは自分の存在が家族に役立っていると感じます。承認される感覚が、もっとやりたいという前向きな気持ちを育ててくれます。
実践してわかった注意点
最初にルールをはっきり決めること
ポイントのつけ方や集計方法、上限金額などは、あいまいにせず最初に明確に決めておきましょう。 子どもも納得してスタートすることで、トラブルになりにくいです。
定期的にリセットして見直すと◎
「今月はトイレ掃除やってみたい!」など、子どもの成長や関心に合わせて内容を見直すのもおすすめ。やり方を一緒に確認したり、コツを教えたりする時間は、親子のいいコミュニケーションにもなります。家事の大変さを知ることで、感謝の気持ちや思いやりも育っていくと感じています。
完璧を求めないのがポイント
お手伝いをはじめたばかりのころは、時間がかかったり、仕上がりが雑だったりすることもあります。やろうとしてくれてる気持ちが大切だと考え、できるだけ口を出さずに見守るようにしました。少しずつ上手になっていく過程を楽しむことも、親の役目だと感じています。
【まとめ】ポイント制度で親子の笑顔を増やす仕組みをつくろう
無理にやらせようとするよりも、自分からやってみたいと思える仕組みがあると、子どもの行動はぐんと変わります。小さな「できた!」の積み重ねが、自信ややる気につながっていくはずです。
お手伝いを通して学べるのは、家のことだけではありません。責任感や計画性、感謝の気持ち、自分で考える力など、子どもにも親にもたくさんの学びがあります。
まずはできそうなことから、ゆるく・楽しく。
ポイント制度が、親子で笑顔になれるきっかけになりますように。
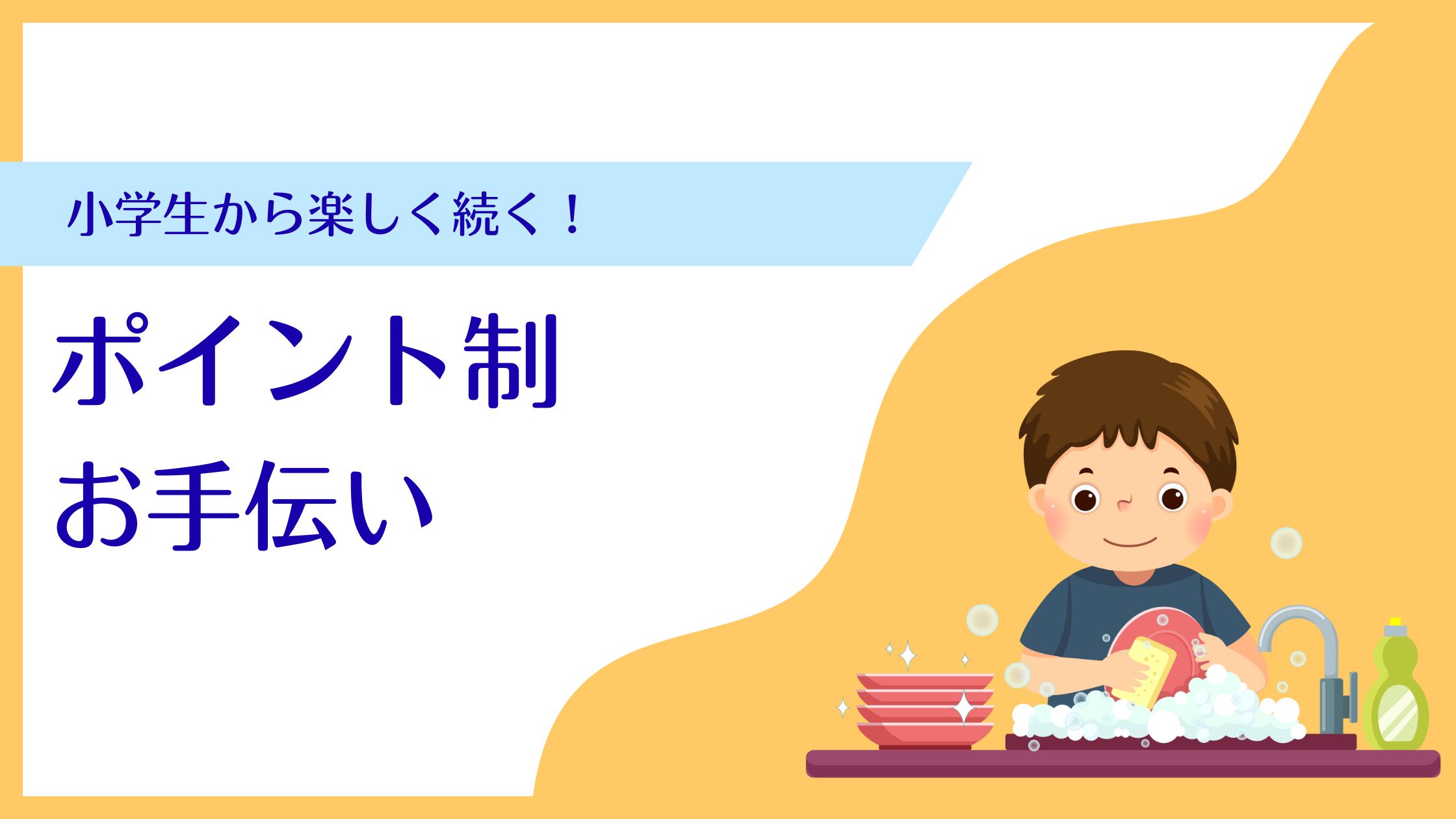
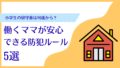

コメント