子どもに何歳から留守番させてよいのか、悩む保護者の方も多いのではないでしょうか。
「そろそろ大丈夫かな」と思いながらも、なかなか踏み出せないものですよね。
この記事では、子どもがひとりで家にいられるかを見極める目安や、防犯ルールの伝え方、安心して留守番を任せるための準備について、わかりやすく解説します。
少しでも不安を減らし、安心して留守番をはじめられるように、ぜひ最後までお読みください。
小学生の留守番は何歳から?
法的には何歳から可能か
日本には「〇歳から留守番してもよい」という明確な決まりはありません。ただし、親が子どもを十分に見守っていないと見られた場合、育児放棄(ネグレクト)と判断されることがあります。
そのため、年齢だけでなく、「子どもがどれだけ分かって行動できるか」や、家の環境、安全のための準備がとても大切です。
実際に多いスタート年齢
留守番をはじめるタイミングとして多いのは、小学1〜3年生です。「小2の夏休みから」や「小1の終わりごろから」など、子どもの様子を見て少しずつチャレンジする家庭が多くあります。
最初は10〜30分ほどの短い時間から試してみて、慣れてきたら少しずつ時間をのばすと安心です。「何年生か」よりも、「その子の性格や状況」に合わせて無理のないタイミングではじめましょう。
なぜ留守番に不安を感じるの?
親が留守番に不安を感じる理由
親が留守番に不安を感じる一番の理由は、万が一のときすぐに対応できないからです。子どもが本当に理解しているかどうか、鍵をきちんと閉められるかといった心配もあります。
特に働くママは、家で子どもが何をしているのかわからない、仕事中に電話がかかってくるかもしれないという不安を感じやすく、精神的な負担になりやすいです。
子どもが感じやすい不安や緊張とは
子どももまた、ひとりで留守番することに不安を感じることがあります。さびしい、音が怖い、もし親が帰ってこなかったらどうしようと心配する子も少なくありません。
こうした気持ちに寄り添いながら、最初は短時間からはじめる、帰る時間を伝えておく、何度か練習するなど、少しずつ慣れていけるようにすると安心です。
最初に教えるべき防犯ルール5つ
①知っている人でもドアは開けない
留守番中は、たとえ知っている人でもドアを開けないように伝えることが大切です。子どもは「優しそう」「近所の人だから」と油断しやすいため、「ママがいるときだけ開けていいよ」と具体的に教えましょう。
インターホンが鳴っても出ない、相手が誰かはあとで親が確認するなどのルールを決めておくと安心です。知らない人が来たときの対応を練習しておくと、子どもも落ち着いて行動できます。
②鍵を安全に使うための管理と対応ルール
鍵は自分の身を守る大切な道具だと伝えましょう。ランドセルの中やネックストラップなど、子どもが管理しやすい場所を決めておくと安心です。
また、鍵をなくしたときの対処法も事前に話し合っておくと落ち着いて対応できます。まず親に電話する、近所の〇〇さんの家に行くなど、行動の流れを決めておきましょう。
③インターホン・電話への対応
インターホンや電話は便利な反面、留守番中の子どもにとっては危険になることもあります。誰が来ても名前を言わない、電話には出ないなど、基本のルールをはっきり決めておきましょう。
電話は留守番電話にしたり、決まった相手にのみ通じるようにすると安心です。スマートフォンを持たせる場合も、使っていい相手や時間を決めておきましょう。
迷ったときは「出ないのが基本」と教えておくことで、子どもも安心して行動できます。
④いざというときの連絡方法と避難行動
万が一にそなえて、子どもが自分で連絡や避難ができるようにしておくことが大切です。まずは、親や祖父母、近所の信頼できる人の電話番号を紙に書き、冷蔵庫など見えやすい場所に貼っておきましょう。
火事や大けがのときは、ためらわずに119番することも教えておきます。 住所や電話番号を言えるよう、練習しておくと安心です。
避難先を一緒に確認しておくと、いざというとき落ち着いて行動できます。
⑤火・電気・水など家の中でのトラブル対策
留守番中に起こる家の中でのトラブルにも、しっかり備えておくことが大切です。電子レンジは使わない、水道は必要なとき以外触らない、ブレーカーはいじらないなど、簡単なルールを決めておきましょう。
コンセントの抜き差しやお風呂場の水も、思わぬ事故につながりやすいです。「ママがいないときは使わない」とはっきり伝えることで、子どもも守りやすくなります。
実際に家の中を一緒にまわり、危ない場所を確認しておくと、しっかり覚えられて安心です。
【まとめ】小学生が安全に留守番できる環境をつくろう
小学生の子どもが安全に留守番できるように、ひとりでお家にいられる年齢の目安や防犯ルール、子どもの気持ちへの寄り添い方を解説してきました。大切なポイントは以下の3つです。
・留守番ができる年齢に決まりはなく、子どもの理解力を見て判断することが大切
・防犯ルールはわかりやすく教え、行動の練習もしておく
・家のルールを決め、安心できる環境をつくる
今できる小さな対策が、大きな安心につながります。ルールを一緒に確認したり、まずは5分の留守番からはじめることで、「自分でできた」と自信を持つきっかけになるでしょう。
自宅のルール表を親子で作って冷蔵庫に貼る、防犯グッズを一緒に選ぶなど、できることからはじめてみてください。子どもの成長を見守りながら、無理のないペースで留守番をサポートしていきたいですね。
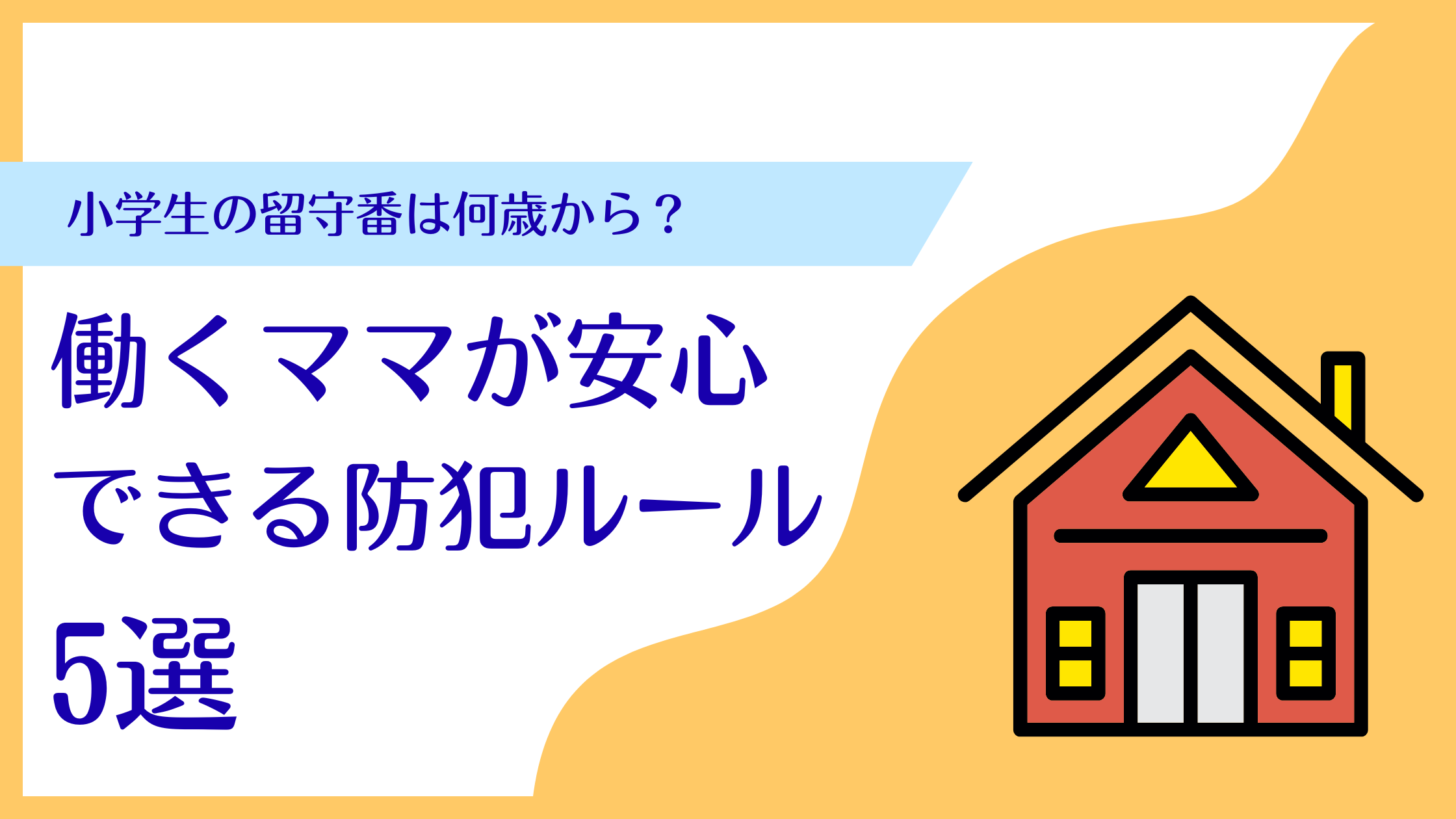

コメント